「SHEINって置き配できるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
忙しい毎日、できれば不在でも荷物をスムーズに受け取りたいと思う方は多いはず。
特にAmazonや楽天で置き配が当たり前になりつつある今、海外通販であるSHEINでも同じように使えるのか気になりますよね。
この記事では、SHEINで置き配ができない理由をわかりやすく解説するとともに、代替手段やよくある誤解、安心して受け取るための工夫までを丁寧にご紹介します。
読み終えるころには、「どうやって受け取ればいいか」「置き配ができないときの対策は?」といったモヤモヤがすっきり解消されているはずです。
安心してお買い物を楽しむためのヒント、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
SHEINでの置き配はできない?その理由を徹底解説

SHEINの配送方法の全体像
SHEINでは、基本的に国内の主要な配送業者を利用して商品を届けています。 配送スピードや追跡サービスも整っており、購入者はアプリやサイトでリアルタイムに確認できます。
SHEINの注文は海外倉庫から発送されるため、国内の通販サイトとは異なる流れを経て届けられます。注文から到着までにかかる日数は通常5〜10日ほどですが、通関手続きなどを挟むことで前後することもあります。
配送業者は注文時に選べないケースが多く、自動的に割り振られるのが一般的です。なお、注文完了後に「追跡番号」が発行され、現在どこに荷物があるのかを確認することができます。
こうした仕組みの違いが、SHEIN独自の配送スタイルにつながっており、国内通販とは一線を画しています。
日本の置き配事情とSHEINの違い
日本ではAmazonや楽天などを中心に、置き配が広く普及しています。玄関前や宅配ボックスへの配達が可能で、不在時でも荷物を受け取れることから、多くの人に支持されています。
一方、SHEINでは現時点で置き配を選択することはできません。これは、海外からの配送体制や、利用する配送業者との契約条件に起因しているためです。さらに、配送トラブルや紛失リスクを回避するため、SHEINでは基本的に対面での受け取りを前提としています。
このように、同じ日本国内で受け取る荷物でも、「どこから」「どのルートで」送られてくるかによって、受け取り方法に違いが生じるのです。
置き配が人気を集める理由とメリット
置き配が選ばれる大きな理由は、「不在時でも荷物を受け取れる」利便性にあります。特に忙しくて日中に在宅できない方や、配達時間に合わせるのが難しい家庭にとっては、再配達の手間が省ける点が非常にありがたいポイントです。
再配達を依頼する手間が省けるため、忙しい方にとって大きなメリットとなります。さらに、近年では環境負荷軽減の観点からも注目されており、再配達回数が減ることでCO2排出の削減にもつながります。
また、玄関先で非対面で受け取れるという点は、防犯や衛生面を気にする方にも人気です。置き配専用バッグやボックスの利用で安全性も高まり、利用者のライフスタイルに柔軟に対応できるサービスとして、今後さらに普及が進むと予想されます。
SHEINの置き配ができない理由
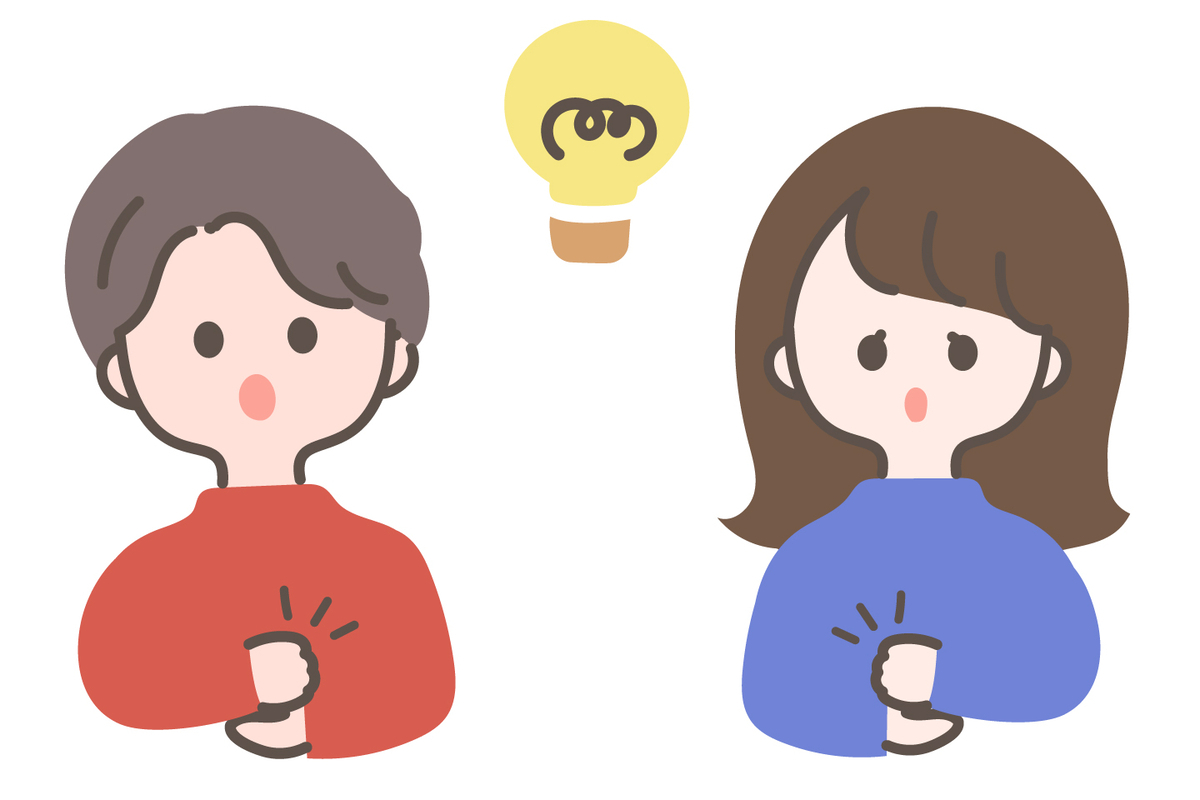
契約している配送業者の仕組み
SHEINは自社で配送網を持たず、複数の配送業者と提携しているため、その業者の対応範囲に準じる形で配送方法が決まります。 日本国内のECサイトであれば、利用者がヤマトや佐川などを選べる場合もありますが、SHEINではこの選択肢は基本的に提供されていません。
業者によっては置き配に対応していても、SHEINがそのサービスを契約していないことが多いため、実際には利用できないケースがほとんどです。これは、SHEIN側がトラブル防止や配送コストの管理を重視している背景もあります。
利用者への配慮による受け取り方法
海外通販という特性上、配送途中でのトラブルや、荷物の誤配送・盗難などのリスクを避けるために、あえて「手渡しでの受け取り」を基本とする体制がとられています。特に海外配送では、現地の倉庫や中継地点を経由するため、荷物の追跡や管理が複雑になりがちです。
そのため、利用者に確実に商品を届ける手段として、置き配ではなく「直接受け取ってもらう」方法が選ばれています。利用者にとっては一手間増えるように感じるかもしれませんが、SHEIN側としては商品到着の確実性を最優先にしているといえます。
国や地域による規制やルール
国や地域によって、置き配に対する法律や業界ルールが異なるため、SHEINがすべての国で同一サービスを提供するのは難しいのが現状です。たとえば、ある国では玄関前に置くだけで配達完了とみなされることもありますが、日本では配達完了の証拠を求められることもあります。
また、地域によってはマンションやアパートの構造上、置き配が禁止されている場所もあります。こうした背景を踏まえると、SHEINが一律に「置き配対応可能」とは言えない理由がよくわかります。
そのため、現時点では「SHEIN=置き配できない」という状況が基本となっているのです。
配送業者ごとの違いを知っておこう

ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の対応
日本国内で主に利用されている配送業者には、ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便などがあります。これらの業者はそれぞれ異なるサービス方針を持っており、置き配に関しても対応の違いがあります。
たとえばヤマト運輸では、玄関前や宅配ボックスへの置き配に比較的柔軟に対応しています。一方で、佐川急便は配達時のトラブル回避のため、受け取りサインを重視する傾向があります。日本郵便では、配達員の判断で置き配されるケースもありますが、確実性にはやや差があると言えます。
こうした違いがある中で、SHEINが特定の業者に限定せず配送を委託していることも、置き配が一律で提供されない理由のひとつになっています。
契約内容やサービス範囲の違い
SHEINが契約している配送業者との間には、一般消費者向けの契約とは異なる「法人契約」や「業務委託契約」が存在します。 これにより、たとえ配送業者が通常サービスで置き配を提供していたとしても、SHEINの契約内容では対象外となっているケースが少なくありません。
さらに、配送先の地域や建物の種類、配達時間帯などによっても、サービスの可否が変わることがあります。たとえば、オートロック付きの集合住宅では、玄関前まで届けられず、置き配自体が不可能な場合もあります。
利用者の立場から見ると「同じ配送業者なのに、なぜ置き配できないの?」と感じるかもしれませんが、その背景には契約内容やシステム上の制約が関係しているのです。
SHEINアプリやサイトでできること

配送設定の確認方法
SHEINではアプリや公式サイトから配送方法や状況を確認できます。 注文履歴ページにアクセスすると、それぞれの注文ごとに「追跡」ボタンが表示されており、現在の配送状況や利用中の配送業者の名前などをチェックできます。
また、「住所情報」や「配送メモ」などの入力項目もあり、受け取りの補足情報を記載することも可能です。ただし、SHEIN側で置き配を許可していない場合、この情報は参考程度にしか使われないため、確実な指定とはなりません。
配送状況の確認はもちろん、細かい受け取り設定まで一括管理できるのがSHEINアプリの強みです。 利用前には、通知設定をONにしておくと、配送ステータスの更新を見逃さずに済みます。
追跡番号のチェックと活用法
注文後に発行される「追跡番号」は、配送状況を把握するうえでとても大切な情報です。この番号を使えば、配送業者の公式サイトでも荷物の詳細を確認することができます。
追跡番号は通常、発送完了後にアプリ内または登録したメールアドレス宛に通知されます。荷物がどこにあるかをリアルタイムで追えるため、「いつ届くのか不安」「外出中に配達されたくない」といった悩みの解消につながります。
特に、配送トラブルが起きた場合には、この追跡番号が解決のカギとなることもあるので、必ず控えておくようにしましょう。
置き配に関する誤解と注意点

「一部では置き配できる?」という勘違い
SNSや口コミなどで、「SHEINの商品が玄関に置かれていた」という体験談を見ることがあります。そのため「SHEINも置き配できるのでは?」と思われがちですが、これは配送員の独自判断や一部例外的な対応によるものであり、公式にはサポートされていない方法です。
実際にはSHEIN側が「置き配指定」を正式に用意しているわけではないため、こうしたケースはあくまで一時的・偶発的な対応と捉えるのが適切です。こうした誤解により、「前回できたから今回もできるはず」と期待すると、荷物の取り扱いや責任の所在が曖昧になってしまう恐れがあります。
置き配が可能だったという体験談を鵜呑みにせず、基本は非対応であることを前提に考えておくのが安心です。
注意しておきたいトラブル事例
置き配が非対応の状態で、配達員が誤って玄関先などに荷物を置いていった場合、トラブルに発展する可能性があります。特に集合住宅などでは共用スペースが多く、荷物が他人の目に触れやすい環境となっていることも。
また、万が一商品がなくなってしまった場合でも、置き配が正式に認められていない以上、補償の対象外になることがほとんどです。これはSHEINだけでなく、配送業者側にも責任の所在が曖昧になるため、解決までに時間を要する可能性があります。
少しでも不安がある場合は、事前に受け取り方法を明確にし、確実に手渡しで受け取る工夫をしておくことが大切です。
置き配を希望する人が取れる工夫

受け取り時間の指定を活用する
受け取り時間帯を指定することで、在宅中に確実に荷物を受け取れる確率を高めることができます。 SHEINでは注文時に細かい時間帯指定はできないものの、配送が国内業者に引き渡された段階で、一部の配送会社では再配達の時間指定が可能となることがあります。
とくにヤマト運輸や日本郵便を利用した場合には、各社の再配達受付ページや公式アプリを通じて、細かな時間指定ができる場合もあります。配送状況をこまめにチェックし、再配達が必要な場合は、できるだけ早く希望の時間を伝えるようにしましょう。
「家にいないから受け取れない」を防ぐには、配送スケジュールに自分から寄り添う工夫も大切です。
家族や友人に代理受け取りをお願いする
自分が受け取れない可能性がある場合は、あらかじめ家族や同居人に事情を伝え、代理で荷物を受け取ってもらえるようお願いしておくと安心です。 SHEINでは署名不要で配達されることが多く、受け取る人が本人でなくても問題ないケースもあります。
ただし、トラブルを避けるためにも「どのくらいの大きさの荷物か」「どこに届く予定か」などの情報を共有しておくとよりスムーズです。受け取り後の保管場所や開封タイミングについても話しておけると安心ですね。
配送通知を見逃さないコツ
配送通知を見逃してしまうと、気づかないうちに不在票だけが残される…ということもあります。通知を確実に受け取るには、SHEINアプリの通知設定をONにしておくことが重要です。
また、配送業者によってはSMSやメールでお届け予定日を知らせてくれる場合もあります。スマホの通知が多くて見落としがちという方は、SHEIN関連の通知だけでも個別に設定を見直すのがおすすめです。
「いつ届くか分からない」を防ぐためにも、通知と追跡番号を活用して、受け取りのタイミングを事前に把握しておきましょう。
海外のSHEINにおける置き配事情

アメリカや欧州の事例
海外、特にアメリカやヨーロッパの一部地域では、置き配がごく一般的な配送スタイルとして根付いています。 たとえばアメリカでは、玄関前やポーチなどに荷物を置くことが標準的な対応とされており、不在時でも配達が完了する仕組みが整備されています。
Amazonなどの大手ECサイトでは、ドライバーが荷物を玄関先に置き、その場で写真を撮って「配達完了」とする流れが浸透しています。防犯カメラの設置が進んでいることもあり、置き配が比較的安心して利用されている背景もあります。
一方でリスクもあり、地域によっては問題も指摘されています。そのため、鍵付きのボックスやドアベル付きカメラの導入など、対策を講じながら置き配を活用している家庭も多いようです。
日本との違いと背景
日本では住宅事情や文化的背景が異なるため、海外のような自由な置き配スタイルが根付きにくいという現実があります。
集合住宅が多く、玄関先が共用スペースとなっている場合が多いため、荷物を無造作に置くとトラブルにつながる可能性が高まります。また、日本では「手渡し文化」が根強く残っており、配達物は直接受け取るべきものという意識も強くあります。
加えて、SHEINのようなグローバル企業では、配送方法を国ごとに細かく分けるのが難しいため、「基本方針として置き配は非対応」としておくことで、トラブル回避を図っている側面もあると考えられます。
こうした背景から、海外では当たり前の置き配が、日本ではまだ限定的なサービスとしてとどまっているのが現状です。
配送トラブルを避けるために利用者ができること

早めの問い合わせと対応
「届かない」「遅れている」と感じたら、迷わず早めに問い合わせをすることが大切です。 SHEINでは注文履歴ページから配送状況を確認できるだけでなく、カスタマーサポートに直接メッセージを送る機能も備えられています。
また、配送業者が国内に引き継いだ段階で、各業者の再配達や問い合わせフォームも利用可能となるため、連携して対応を進めることができます。商品が届かない状況を長く放置せず、SHEINまたは配送業者に迅速に連絡を入れることで、解決が早まる可能性が高まります。
万が一トラブルが発生した際も、履歴やスクリーンショットを残しておくことで、よりスムーズな対応につながります。
配送状況のこまめなチェック
追跡番号を活用して、荷物がどこまで届いているのかをこまめに確認する習慣をつけておくことも、トラブル回避の一歩です。 特に、通関手続き中や輸送中の段階ではステータスが長時間変わらないこともありますが、定期的にチェックすることで異常に早く気づける場合があります。
また、国内配送業者に切り替わったタイミングで通知が来ることもあるため、アプリの通知やメールを見逃さないようにしましょう。配送が遅れていると感じたら、まず追跡情報を確認し、必要に応じて問い合わせへと進めるのが基本です。
「いつの間にか不在票だけが入っていた」「受け取りそびれた」を防ぐためにも、配送状況には日々目を向けておくと安心です。
よくある質問(FAQ)

置き配できない場合の対処法
SHEINで置き配ができないと分かったとき、まず検討したいのが代替の受け取り方法です。 たとえば、コンビニ受け取りや宅配ボックスの活用、家族への代理受け取りなど、状況に応じて柔軟に選ぶことができます。
配送前であれば「配送メモ」に要望を記載する、または配送業者の受け取り日時変更サービスを使って、できるだけ都合の良い時間帯に合わせるのもおすすめです。
自分のライフスタイルや在宅状況に合わせて、受け取り方法を工夫することが満足度の高いショッピング体験につながります。
代替受け取りサービスの選び方
どの方法が自分にとって便利かは、「いつ受け取りたいか」「どこで受け取りたいか」「誰が受け取れるか」によって変わります。仕事や家事で忙しい方は、24時間営業のコンビニを選ぶと自由度が高くなりますし、家に宅配ボックスがある方は非対面でスムーズに受け取ることができます。
家族に受け取ってもらう場合は、事前に配達予定や内容を共有しておくとトラブルも避けられます。
一度でも受け取りに手間取った経験があるなら、自分に合った受け取り方法を見直してみるのがおすすめです。
配送中にトラブルが起きたらどうする?
配送中に荷物が止まってしまったり、遅延している場合には、まずはSHEINアプリでステータスを確認し、必要であれば問い合わせを行いましょう。アプリ内のカスタマーサポートでは、チャット形式で質問や報告ができ、比較的スピーディーに対応してもらえます。
また、配送業者の問い合わせ窓口も併用すると、現地での荷物の動きについて詳しく知ることができる場合もあります。問い合わせの際は「注文番号」「追跡番号」「ステータスのスクリーンショット」などを準備しておくと、やりとりがスムーズになります。
不安な気持ちを長引かせず、行動に移すことで早期解決につながります。
まとめと今後の展望

SHEINの配送サービスは今後どうなる?
現時点ではSHEINで置き配を指定することはできませんが、今後のサービス拡充によって対応が検討される可能性は十分にあります。
日本での利用者が増え、利便性や要望の声が高まることで、企業側も柔軟な受け取り方法の導入を検討する流れになるかもしれません。
実際、他の海外ECサイトでは日本向けに配送方法を見直す動きも見られており、SHEINも日本市場に合わせた独自の改善が期待されています。
利用者ニーズに応じた変化の可能性
これからもEC市場は拡大を続けると予想されており、利便性と安全性を両立する新しい配送方法への需要が高まっていくでしょう。 そのなかで、置き配というスタイルも、日本の暮らしに合わせて少しずつ受け入れられていく可能性があります。
SHEINとしても、ユーザーの声を受けて柔軟な対応策を講じることがブランドの信頼につながるため、今後のアップデートに注目しておきたいところです。
安心で便利な受け取りのために大切なこと
SHEINでは現在のところ置き配ができませんが、コンビニ受け取りや宅配ボックス、家族による代理受け取りなど、多様な工夫によって快適に商品を受け取る方法はたくさんあります。
自分にとって無理のない受け取りスタイルを見つけ、配送状況をしっかり確認することで、トラブルの予防にもつながります。
これからも変化する配送スタイルに柔軟に対応しながら、安心してお買い物を楽しんでいきましょう。